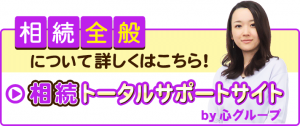- トップ
- ブログ
ブログ
未分割財産がある場合で、寄与分がある場合の遺留分の計算式
みなさんこんにちは!
名古屋もだいぶ暖かくなってきました。
もっとも、季節の変わり目で、体調を崩しやすい時期ですので、みなさんもお体にはお気を付けください。
さて、本日は、前回に引き続き、遺留分に関して、「未分割財産がある場合で、寄与分がある場合の遺留分の計算式」という内容でお話していこうと思います。
まず、遺留分侵害額の請求額(遺留分請求額)についてですが、計算式は、以下のとおりです。
遺留分侵害額=「遺留分額-遺留分権利者が受けた贈与・遺贈・特別受益の額」-「遺産分割の対象財産がある場合において遺留分権利者の具体的相続分に相当する額」+「遺留分権利者が負担する債務(遺留分権利者承継債務)」
たとえば、
被相続人 父
遺産(遺留分算定の基礎財産額) 1億円
相続人 長男、長女
生前贈与 長女は、父が亡くなる12年前に、500万円の生前贈与(特別受益)がある。
遺言 長男に8000万円を相続させる(2000万円については未分割)
という事例で考えてみます。
長女の「遺留分額」は、1億円の4分の1の2500万円です。
未分割財産の分け方について、遺言の内容と長女への500万円の特別受益も加味する場合、未分割財産2000万円について、すべて長女が取得することになります。
以下は、計算式です。
【計算式】
2000万円(未分割財産)+8000万円(長男への相続)+500万円(長女への生前贈与)=1億500万円(みなし相続財産)
長男取得額=1億500万円÷2-8000万円(長男への相続)≦0となるため、未分割財産2000万円について長女が取得。
よって、長女の遺留分侵害額は、2500万円-500万円-2000万円となり、結果は0円となります。
それでは、父の生前、長女が父の介護を一生懸命行い、200万円の寄与分が認められた場合で考えてみます。
遺留分を計算するうえでの「遺留分権利者が受けた贈与・遺贈・特別受益の額」について、未分割財産の分け方は、寄与分は考慮しないという考え方があります。
これを前提とすると、遺留分の計算上、未分割財産について、やはり長女が全額取得することになります。
以下は、計算式です。
【計算式】
2000万円(未分割財産)+8000万円(長男への相続)+500万円(長女への生前贈与)=1億500万円(みなし相続財産)
長男取得額=1億500万円÷2-8000万円(長男への相続)≦0となるため、未分割財産2000万円について長女が取得。
そのため、この考えを前提とすると、長女は200万円の寄与分は認められるが、それが遺留分の計算上、反映されないということになります。
結果として、長女は、介護を一生懸命行い200万円の寄与分はあるが、長女の取得財産額には影響しないということになります。
このように、遺留分の場面においては、寄与分があったとしても、金額に影響しない場合があるため、介護等を一生懸命行ってきた相続人としては、寄与分を主張するよりも、遺言書の書き換えを生前に行った方が良いでしょう。
さて、次回は、相続放棄に関連して、「他の相続人による相続の承認又は放棄の期間の伸長申立」についてお話いたします。
それではまた!
未分割財産がある場合の遺留分の計算式
みなさんこんにちは!
名古屋もまだまだ寒い日が続いております。
風邪やコロナ、インフルエンザもまだまだ流行っておりますので、お体にはお気を付けください。
さて、本日は、前回に引き続き、遺留分に関して、「未分割財産がある場合の遺留分の計算式」についてお話していこうと思います。
まず、前回までの復習として、遺留分額の計算式としては、
遺留分=「遺留分を算定するための財産の価額(基礎財産額)」×「個別的遺留分割合」となります。
また、「基礎財産額」については、「被相続人が相続開始時において有した財産の価額」+「被相続人が贈与した財産の価額」-(相続債務の全額)となります。
具体的な遺留分侵害額については、
遺留分侵害額=「遺留分額-遺留分権利者が受けた贈与・遺贈・特別受益の額」-「遺産分割の対象財産がある場合において遺留分権利者の具体的相続分に相当する額」+「遺留分権利者が負担する債務(遺留分権利者承継債務)」となります。
この点、「遺産分割の対象財産がある場合において遺留分権利者の具体的相続分に相当する額」について、未分割財産があった場合の処理について、今回お話していきます。
さて、前置きが長くなってしまいましたが、「遺産分割の対象財産がある場合において遺留分権利者の具体的相続分に相当する額」について、たとえば、以下の事例で考えてみます。
被相続人(父)
相続人:長男、長女
遺言書の内容:長男に自宅土地建物を相続させる
遺産:自宅土地建物(時価7000万円)
預貯金1000万円
この場合、遺留分額としては、遺留分を算定するための財産の価額(基礎財産額)が合計の8000万円となり、長女の遺留分としては、その4分の1の2000万円となります。
ここで、遺言書の対象外となっている1000万円についてですが、そもそも、この1000万円をどう分けるのかについては、長男と長女との遺産分割の結果によります。
考え方の一つとして、長男は、遺言書によってすでに7000万円相当の自宅建物を相続しているため、残りの預貯金全てを長女が相続するということが考えられます。
他方、当該7000万円については、持ち戻し免除の意思表示がされているものとして、預貯金を500万円ずつで分けるという考え方もあります。
いずれの分け方にする方は、当事者間で話し合いがまとまらなければ、遺産分割審判で決着がつくことになります。
遺留分に関しては、仮に長女が1000万円を取得することになると、長女の遺留分の2000万円から1000万円を控除した1000万円が遺留分侵害額ということになります。
この場合、長女は、長男に対して、1000万円の遺留分侵害額請求を行うことになります。
さて、次回は、今回に引き続き遺留分に関して、よりマニアックな論点として、「未分割財産がある場合で、寄与分がある場合の遺留分の計算式」についてお話していこうと思います。
それではまた!
遺留分侵害額請求の計算式
みなさんこんにちは!
名古屋も時々、雪が降るなど、めっきり寒くなってきました。
インフルエンザやコロナ、風邪も流行っておりますので、みなさんもお体には十分にお気を付けください。
さて本日は、「遺留分侵害額請求の計算式」について、お話していこうと思います。
そもそも、遺留分とは、簡単にいうと相続人に認められた最低限度の権利のことをいいます。
また、遺留分の金額については、遺言書や生前贈与の内容、相続人の範囲、遺産の内容等で、大きく異なってきます。
以下では、簡単な事例を用いて、遺留分侵害額請求の計算式について、ご説明いたします。
【事案】
父が亡くなり、相続人は、長男と二男のみです。
父は、生前、長男家族と同居しており、長男家族が自身の介護をしてくれていたため、財産すべてを長男に相続させる旨の遺言書を残していました。
父は、令和7年2月1日に亡くなりました。
父の死後、長男は、父が残した遺言書どおりに遺産を分ける旨を二男に伝えたところ、二男は、長男に対して、遺留分侵害額請求をしました。
【父の遺産】
父の相続開始時(亡くなった時点)の遺産内容は、以下のとおりです。
自宅土地建物 時価3000万円(固定資産税評価額は2400万円)
預貯金 1100万円
父の医療費(死後に支払い) 10万円
父から長男からの生前贈与(令和5年1月1日) 1000万円
【遺留分額の計算式】
遺留分額=「遺留分を算定するための財産の価額(基礎財産額)」×「個別的遺留分割合」となります。
「基礎財産額」については、「被相続人が相続開始時において有した財産の価額」+「被相続人が贈与した財産の価額」-(相続債務の全額)となります。
1 基礎財産額について
自宅土地建物などの不動産の評価については、原則、時価を基準に評価します。
もっとも、遺留分請求者(二男)と遺留分を請求される人(長男)が合意をすれば、固定資産税評価額を基準にすることができます。
今回は、長男と二男との間で合意がまとまらなかったとして、時価を基準に評価します。
そのため、自宅土地建物の不動産価格は、3000万円となります。
よって、基礎財産額は、5090万円となります(遺産額に生前贈与を加え、債務を減額した額)。
2 個別的遺留分割合
二男の法定相続分は、2分の1であり、その半分の4分の1が個別的遺留分となります。
3 二男の遺留分請求額
よって、二男の遺留分額は、1272万5000円となります。
このように、遺留分の計算方法としては、それほど複雑ではありませんが、計算式を間違えてしまうと、遺留分額も変わってしまうため、注意が必要です。
さて、次回は、今回に引き続き、「未分割財産がある場合の遺留分の計算式」について、お話していこうと思います。
それではまた!
相続税~非上場株式の評価⑩純資産価額方式
みなさんこんにちは!
名古屋もかなり寒くなり、インフルエンザ、コロナ、風邪がかなり流行ってきています。
これらが同時にかかってしまうと、重症化するおそれもありますので、みなさんもお体には、お気を付けください。
さて、今回は、前回に引き続き、相続税における非上場株式の評価について「相続税~非上場株式の評価⑩純資産価額方式」に関して、事例も交えてお話していこうと思います。
まず、純資産価額としては、①総資産価額(相続税評価額によって計算した金額)から②負債の金額(相続税評価額によって計算した金額)と③評価差額に対する法人税額等に相当する金額を控除する方法により算出します。
たとえば、ある名古屋の会社について、
①相続税評価額によって計算された純資産価額が3億円、
②負債の金額が1億、
④帳簿価格によって計算された純資産価額が2億円、
⑤負債総額が1億円
の場合で考えてみます。
まず、③評価差額に対する法人税額等に相当する金額を算出します。
算出方法としては、①相続税評価額によって計算した総遺産価額から②負債の金額を控除した金額と、④帳簿価格によって計算した純資産価額から⑤負債の金額を控除した金額との差に37%を乗じて計算します。
【計算式:{(①-②)-(④-⑤)}×37%】
なお、帳簿価格によって計算した純資産価額から負債の金額を控除した金額の差がマイナスの場合は、0として評価します。
さきほどの具体例に当てはめると、
①-②は2億円、
④-⑤は1億円となるため、
2億円-1億円の1億円の37%である3700万円について、法人税額等に相当する金額となります。
そのため、純資産価額は
①-②-3700万円となり、1億6300万円となります。
また、発行済み株式総数が2万株の場合は、1株当たりの評価額は、1億6300万円を2万株で割った、8150円となります。
なお、議決権割合が50%以下の同族株主グループに属する株主が取得した株式の価額は、この金額の80%相当額となり、1株当たり6520円となります。
このように、純資産価額方式での非上場の株式の評価については、単純な計算式で計算することができますが、相続税評価額による純資産価額や負債を算出することに労力がかかるため、やはり非上場会社の株式の評価については、相続税に詳しい税理士にご依頼されることをおすすめします。
さて、次回は、相続税から離れ、遺留分に関して、「遺留分侵害額請求の計算式」と題してお話していこうと思います。
それではまた!
相続税~非上場株式の評価⑩純資産価額方式
みなさんこんにちは!
名古屋もだいぶ寒くなり、インフルエンザも流行りだしてきましたので、みなさんもお体にはお気を付けください。
さて、今回は、次回に引き続き、非上場株式の評価について、「相続税~非上場株式の評価⑩純資産価額方式」としてお話していきます。
まず、純資産価額方式は、評価の対象となる会社の貸借対照表の財産を相続税評価額によって評価していくことになります。
評価の方法については、基本的に相続税財産評価に関する基本通達(国税庁:財産評価基本通達)に基づき算出します。
たとえば、貸借対照表において、
預金 8500万円
貸付金 500万円
建物 2000万円
土地 5000万円
買掛金 3000万円
という記載があった場合、それぞれを相続税評価額に評価し直します。
たとえば、預貯金については、課税時期現在における既経過利子の額から源泉徴収されるべき所得税等の額に相当する金額を控除した金額を控除した金額を加算します。
なお、普通預金、当座預金など既経過利息が少額の場合は、そのままの金額を記載します。
そのため、預貯金について、すべて普通預金であった場合、額面どおりの金額が相続税評価額となり、先ほどの事例では、8500万円となります。
他方、預貯金のうち定期預金があった場合で、既経過利息が10万円、源泉徴収税額が2万300円の場合、8507万9700円が相続税評価額となります。
また、貸付金については、課税時期現在における既経過利息の額を加算し、回収不能額を減算した金額となります。
そのため、貸付金500万円の既経過利息が10万円、回収不能額が200万円の場合、310万円が相続税評価額となります。
建物については、基本的に固定資産税評価額で評価しますが、課税時期以前3年以内に取得した家屋等の場合、課税時期における通常の取引価格により評価します。
そのため、当該建物を3年より前に購入した場合は、帳簿価格よりも通常低くなる固定資産税評価額で計算されますが、3年以内に購入した場合は、購入した金額に近い金額で評価することになります。
たとえば、建物を10年前に購入した場合、建物の固定資産税評価額が500万円であれば、500万円として評価しますが、購入したのが2年前であり2000万円で購入した場合、建物の固定資産税評価額がたとえ800万円であったとしても、2000万円に近い金額で評価することになります。
土地も建物と同様、課税時期以前3年以内に取得した土地等かによって、金額が異なります。
最後に、買掛金については、負債の部として計上されていますが、買掛金の場合は、課税時期現在において、事実上支払いを要しない金額を減算することになります。
そのため、3000万円の買掛金のうち、1000万円について支払いを要しない場合、2000万円が負債として計上されます。
このように、純資産価額方式の場合、貸借対照表の金額を相続税評価額に引き直して計算する必要があるため、会社が多くの不動産を持っている場合や会社が非上場の株式を保有している場合は、評価するだけでもかなりの時間と労力を要することになります。
そのため、非上場株式が遺産にある場合は、なるべく早めに税理士等の専門家にご相談された方がよく、期限が迫った状態で税理士に依頼しても、期限内に相続税の申告が出来ない可能性もありますので、注意が必要です。
さて、次回は、今回に引き続き、純資産課税方式について、特に法人税について、事例を交えて、「相続税~非上場株式の評価⑩純資産価額方式」として、ご説明しようと思います。
それではまた!
相続税~非上場株式の評価⑨純資産価額方式
みなさんこんにちは!
名古屋も朝夕はだいぶ肌寒くなってまいりました。
季節の変わり目ですので、お体にはお気を付けください。
さて、本日は、「相続税~非上場株式の評価⑨純資産価額方式」と題して、非上場株式における純資産価額方式による評価方法についてお話していきます。
純資産価額方式とは、非上場株を評価する際に、仮に対象の評価会社が解散した場合に、その会社の株主に分配されるはずの財産価値で評価しようとするものです。
また、「分配されるはずの財産価値」とは、相続開始時点において、会社が保有する個々の資産の相続税評価額を基に算出することになります。
そのため、会社が土地を持っている場合や土地を借りている場合は、個々の土地や借地権について、評価を行う必要があります。
純資産価額方式の注意点として、会社の清算価値で株式を評価するため、事業が継続している会社の企業価値を十分に反映しているわけではなく、実際の時価と乖離する場合があります。
なお、遺産分割や遺留分において、実際の時価が問題になる場合は、相続税評価額によるもののほか、公認会計士等に鑑定を依頼する場合もあります。
さて、具体的な純資産価額方式の計算方法ですが、
①相続開始日の貸借対照表を作成する
②資産を全て時価に置き換える
③負債を時価に置き換える
④純資産価額を計算し、1株あたりの評価額を算出する
というような流れで行います。
まず、①相続開始時の貸借対照表については、通常の決算を行うのと同じ要領で作成します。
会社に顧問税理士等がいる場合は、作ってもらうこともできます。
②資産の時価評価については、土地について相続税評価額で計算します。
また、前払金や繰延資産、繰延税金資産は、財産性がないため、0円で評価するなど、資産を時価として評価していきます。
③負債を時価評価については、各種引当金は、負債に含めず0円として評価し、被相続人の退職金や法人税や消費税の未払金については、計上して負債を評価していくことになります。
④資産と負債を時価評価できれば、資産から負債を控除して純資産価額を算出し、それに対して発行済み株式総数で割ることで、1株当たりの評価額を算出することができます。
このように、純資産価額方式については、時価を算出することによって会社の株式を評価していくものであり、一般的には、類似業種比準方式による評価額よりも高くなる傾向にあります。
さて、次回は、引き続き、純資産価額方式について、事例を交えて、「相続税~非上場株式の評価⑩純資産価額方式」として、ご説明しようと思います。
それではまた!
相続税~非上場株式の評価⑧類似業種比準方式
みなさんこんにちは!
名古屋もだいぶ涼しくなってきました。
季節の変わり目ですので、お体にはお気を付けください。
さて、今回は、前回に引き続き、「相続税~非上場株式の評価⑧類似業種比準方式」として、類似業種比準方式を使った非上場株式の評価について、具体例をもとに説明していきたいと思います。
【設例】
≪評価会社のデータ≫
業種:紳士服卸売業
企業規模区分:中会社の中(斟酌率0.6)
直前期末の資本金額:4000万円
直前期末の発行済み株式数:8万株
①1株当たりの資本金額:500円(株式額面金額500万円)
1株当たりの資本金額を50円とした場合の発行済み株式数(資本金額÷50円):80万株
②年間配当金額(総額):直前期400万円、前々期500万円、前々期の前記600万円
<1株当たり配当金額:450万円(直前2期平均)÷80万株=5.6円>
③利益金額(法人税課税所得金額):直前期8000万円、前々期7000万円
非経常的な利益損金額:なし、受取配当等の益金不算入額:なし
<1株当たり利益金額:{(8000万円+7000万円)÷2}÷80万株=93.75
円>
④純資産価額:8000万円(資本金4000万円、利益積立金2億円)
<1株当たり純資産価額:2億4000万円÷80万株=300円>
⑤類似業種のデータ
業種目:繊維・衣服等卸売業
株価:479円(課税時期の属する月の数値を採用)
1株当たり配当金額:5.2円
1株当たり利益金額:51円
1株当たり純資産価額:376円
具体的な計算式としては、以下のとおりです。
類似業種の株価(479円)×(((5.6円(評価会社の1株当たりの配当金額)÷5.2円(類似業種の1株当たりの配当金額))+(93.75(評価会社の1株当たりの利益金額)÷51円(類似業種の1株当たりの利益金額))+(300円(評価会社の1株当たりの純資産価額)÷376円(類似業種の1株当たりの純資産価額)))÷3×0.6(斟酌率)500円(1株当たりの資本金等の額)÷50円=3557円(類似業種比準価額)(端数切捨て)
このように、類似業種比準方式による評価を行います。
もっとも、実際の申告を行う場合は、各書類を読み解く必要があるため、評価にご不安な場合は、専門家にご相談ください。
さて、次回は、純資産価額方式による非上場の評価について、「相続税~非上場株式の評価⑨純資産価額方式」として、お話していこうと思います。
それではまた!
相続税~非上場株式の評価⑦類似業種比準方式
みなさんこんにちは!
蒸し暑い日が続きますが、名古屋でもコロナが流行ってきましたので、みなさんも、お体には、どうぞお気を付けくださいませ。
さて、本日は、前回に引き続きまして、「相続税~非上場株式の評価⑦類似業種比準方式」と題して、類似業種比準方式による株価算定について、お話していこうと思います。
前回の記事で、類似業種の調べ方をご説明しましたので、次に、類似業種の株価と比準要素の数値を調べます。
まずは、類似業種の株価については、国税庁が発表しているデータを確認することになります。
なお、令和6年度分の類似業種の株価は、以下の国税庁のホームページ(類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別価格等)をご参照ください。
国税庁:令和6年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について(法令解釈通達)
また、株価については、基本的に以下の3つの株価のうち、最も低い金額を選択することになります。
①課税時期の属する月以前2年間の平均株価
②類似業種の前年平均株価
③課税時期の属する月以前3ヶ月間の類似業種の株価のうち最も低い株価
たとえば、課税時期が5月、類似業種が番号81の「織物・衣服・身の回り品小売業」の場合、
①は712円
②は738円
③は722円(3月763円、4月437円、5月722円のうち、最低価格)
となり、これらの最低価格である①712円の金額を株価として、採用することになります。
次に、評価する評価会社の比準3要素である「配当金額」「利益金額」「簿価純資産価額」のそれぞれの数値を確認します。
なお、類似業種における比準3要素である「配当金額」「利益金額」「簿価純資産価額」については、さきほどの類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別価格等に記載されています。
⑴ まずは、評価会社の発行済みの株式を求めます。
これは、実際の発行済み株式数ではなく、一律、以下の計算式で求めた金額を使います。
評価会社の発行済み株式数=直前期末における資本金額÷50円
たとえば、直前期末における資本金の金額が5000万円の場合、発行済み株式数は、100万株となります。
⑵ 次に、評価会社の1株あたりの配当金額を求めます。
計算式は、
直前期末以前2年間の配当金額の合計額×2分の1÷直前期末における発行済み株式数(さきほどの⑴で求めた株式数)となります。
なお、無配当の場合は、0円となり、特別配当などの特殊な配当がある場合は、その部分は除外されます。
⑶ 評価会社の1株あたりの利益金額を求めます。
計算式は、
直前期末以前1年間の利益金額÷直前期末における発行済み株式数(さきほどの⑴で求めた株式数)となります。
なお、直前期末以前1年間の利益金額については、法人税法上の課税所得金額を基本とし、非経常的な利益(固定資産たる不動産の売却など)や配当に係る所得税を控除し、益金に算入されなかった剰余金の配当(受取配当益金不算入金額)や損金の額に算入した繰越欠損金控除額を加算して求めます。
⑷ 評価会社の1株当たり純資産価額を求めます。
計算式は、
直前期末における資本金等の額及び利益積立金額の合計額÷直前期末における発行済み株式数(さきほどの⑴で求めた株式数)となります。
⑸ 比準要素の時期
評価会社の比準要素の時期としては、基本的には算出する期の直前期末となりますが、利益金額については、直前期末以前の2年間分の利益金額を合計して、それを2分の1にした数値を利用することも可能です。
⑹ 類似業種比準方式による評価とならない場合
評価会社の比準3要素のうち、配当金額は、無配であれば「0」となり、利益金額は、直前2期の課税所得が0円以下である場合などは、「0」になります。
また、純資産価額は、債務超過であれば「0」となります。
その結果、直前期末と前々期末の比準3要素のうち2つが「0」の会社(比準要素1の会社)、または、直前期末の比準3要素がすべて「0」の会社は、特定の評価会社となり、原則として類似業種比準価額は用いられず、純資産価額方式による評価となります。
⑺ 斟酌率の確認
評価会社と類似業種とは、当然、社会的な信用度や株式の売却の難易度等も変わってくるため、株価も当然、大きく異なります。
そこで、最後に、斟酌率をかけて、株価の調整を行います。
具体的には、比準要素によって比準されて算出された株価に、以下の斟酌率を掛けます。
大会社 0.7
中会社 0.6
小会社 0.5
⑻ 具体的な計算方法
これまで計算してきた金額をもとに、類似業種比準価額を求めます。
具体的には、
類似業種株価×{(評価会社の1株当たりの配当金額÷課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの配当金額)+(評価会社の1株当たりの利益金額÷課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの年利益金額)+(評価会社の1株当たりの純資産価額÷課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの純資産価額)÷3}×斟酌率
となります。
なお、計算式の表としては、国税庁のホームページもご確認ください。
国税庁:類似業種比準価額
このように、類似業種比準価額の評価については、かなり複雑なものとなっておりますので、計算する際は、十分にご注意ください。
さて、次回は、今回、類似業種比準方式の計算式をお伝えしたため、具体的な事例をもとに、計算方法のおさらいをしたく、「相続税~非上場株式の評価⑧類似業種比準方式」として、お話ししようと思います。
それではまた!
相続税~非上場株式の評価⑥類似業種比準方式
みなさんこんにちは!
名古屋もかなり熱くなり、熱中症が心配な季節になりました。
みなさまもこまめに水分補給をしていただき、お体にはお気を付けください。
さて、本日は、「相続税~非上場株式の評価⑥類似業種比準方式」についてお話していこうと思います。
まず、類似業種比準方式とは、評価したい非上場会社(以下、「評価会社」といいます。)の株式と事業内容が類似している上場会社(以下「類似業種」といいます)の1株あたりの株価を参考にして、当該非上場株式の株式を評価する方式です。
類似業種比準方式による株式算定の場合、一般的に、純資産方式による株式算定額よりも低くなる傾向にあります。
実際、類似業種比準方式の方が、純資産価額の半額以下というような事例も多くあります。
そのため、相続税における会社算定を行う際、大会社の場合は、類似業種比準方式と純資産価額方式との選択となるため、評価額を低くしたい場合は、一般に類似業種比準方式を採用した方が良いでしょう。
また、中会社の場合も、類似業種比準方式と純資産価額方式の併用か、純資産価額方式の選択ができます。
また、小会社の場合は、原則、純資産価額方式ですが、類似業種比準方式と純資産価額方式の併用を選択することもできます。
そのため、いずれの会社規模であっても、それぞれ純資産価額方式と類似業種比準方式のどちらが株式評価の算定に有利か計算する必要があります。
さて、具体的な類似比準方式の評価方法ですが、まずは、類似業種を調べるところから始めます。
類似業種については、まず、総務省が発表している「日本標準産業分類」により会社を分類します(日本標準産業分類については、以下の法務省のホームページをご確認ください。
https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/R05index.htm)
次に、国税庁が公表している「日本標準産業分類の分類項目と類似業種比準価額計算上の業種目との対比表」をもとに、評価会社がどの類似業種に当たるかを判断します(詳細は、以下の国税庁のホームページをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hyoka/170613/01.htm
これによって、類似業種が確認できましたら、次に類似業種の株価と比準要素を調べます。
こちらについては、次回の記事にてご説明します。
それでは、次回については、「相続税~非上場株式の評価⑦類似業種比準方式」と題して、類似業種比準方式の算定の続きについてお話していこうと思います。
それではまた!
相続税~非上場株式の評価⑤会社規模の判定
みなさんこんにちは
名古屋もだいぶ暑くなってきました。
部屋でも熱中症になる危険性もありますので、お体にはお気を付けください。
さて、本日は、前回に引き続き「相続税~非上場株式の評価⑤会社規模の判定」についてお話していこうと思います。
まず、株主の判定を行い、また、特殊な会社でない一般の会社の場合、次に、会社規模の判定を行い、どのような評価方法で計算するのかを判断していきます。
会社については、大会社、小会社、中会社の3つに分けられます。
大会社にあたる場合は、原則として、類似業種比準方式により評価することになります。
類似業種比準方式とは、簡単にいうと、上場している類似の業種の株価を参考に、株式の価額を算出していく方法のことをいい、一般的に類似業種比準方式によって評価した方が、評価額は低くなります。
小会社にあたる場合は、原則として、純資産価額方式により評価することになります。
純資産価額方式とは、簡単にいうと、会社の総資産や負債を評価して、株式を算出していく方法のことをいい、一般的に、類似業種比準方式に比べて、評価額は高くなります。
最後に、中会社にあたる場合は、大会社と小会社の評価方法を併用して評価することになります。
このように、会社規模によって、評価の方法が異なってきます。
それでは、具体的に会社規模の判定ですが、まず、従業員数が70人以上の場合には、それだけで会社の規模が大きいということで、大会社に該当します。
大会社に該当した場合は、それ以降の判定は不要になります。
次に、従業員が70名未満の場合には、①「会社の純資産額と従業員数」と「取引金額」の組み合わせによって判定することになります。
たとえば、小売業で、従業員が15人、総資産価額が6億円、売り上げが17億円の場合は、中会社となります。
なお、中会社でも、3種類あり、類似業種比準方式と純資産価額方式を適用できる割合が異なってきます。
このように、非上場の株式を評価するにあたっては、会社規模の判定を行い、大、中、小のどの会社の規模になるかによって、評価方法が異なり、結果として評価額も異なってきます。
さて、次回は、「相続税~非上場株式の評価⑥類似業種比準方式」についてお話していこうと思います。
それではまた!