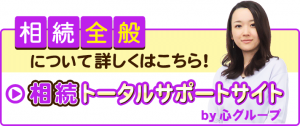遺留分対策
未分割財産がある場合で、寄与分がある場合の遺留分の計算式
みなさんこんにちは!
名古屋もだいぶ暖かくなってきました。
もっとも、季節の変わり目で、体調を崩しやすい時期ですので、みなさんもお体にはお気を付けください。
さて、本日は、前回に引き続き、遺留分に関して、「未分割財産がある場合で、寄与分がある場合の遺留分の計算式」という内容でお話していこうと思います。
まず、遺留分侵害額の請求額(遺留分請求額)についてですが、計算式は、以下のとおりです。
遺留分侵害額=「遺留分額-遺留分権利者が受けた贈与・遺贈・特別受益の額」-「遺産分割の対象財産がある場合において遺留分権利者の具体的相続分に相当する額」+「遺留分権利者が負担する債務(遺留分権利者承継債務)」
たとえば、
被相続人 父
遺産(遺留分算定の基礎財産額) 1億円
相続人 長男、長女
生前贈与 長女は、父が亡くなる12年前に、500万円の生前贈与(特別受益)がある。
遺言 長男に8000万円を相続させる(2000万円については未分割)
という事例で考えてみます。
長女の「遺留分額」は、1億円の4分の1の2500万円です。
未分割財産の分け方について、遺言の内容と長女への500万円の特別受益も加味する場合、未分割財産2000万円について、すべて長女が取得することになります。
以下は、計算式です。
【計算式】
2000万円(未分割財産)+8000万円(長男への相続)+500万円(長女への生前贈与)=1億500万円(みなし相続財産)
長男取得額=1億500万円÷2-8000万円(長男への相続)≦0となるため、未分割財産2000万円について長女が取得。
よって、長女の遺留分侵害額は、2500万円-500万円-2000万円となり、結果は0円となります。
それでは、父の生前、長女が父の介護を一生懸命行い、200万円の寄与分が認められた場合で考えてみます。
遺留分を計算するうえでの「遺留分権利者が受けた贈与・遺贈・特別受益の額」について、未分割財産の分け方は、寄与分は考慮しないという考え方があります。
これを前提とすると、遺留分の計算上、未分割財産について、やはり長女が全額取得することになります。
以下は、計算式です。
【計算式】
2000万円(未分割財産)+8000万円(長男への相続)+500万円(長女への生前贈与)=1億500万円(みなし相続財産)
長男取得額=1億500万円÷2-8000万円(長男への相続)≦0となるため、未分割財産2000万円について長女が取得。
そのため、この考えを前提とすると、長女は200万円の寄与分は認められるが、それが遺留分の計算上、反映されないということになります。
結果として、長女は、介護を一生懸命行い200万円の寄与分はあるが、長女の取得財産額には影響しないということになります。
このように、遺留分の場面においては、寄与分があったとしても、金額に影響しない場合があるため、介護等を一生懸命行ってきた相続人としては、寄与分を主張するよりも、遺言書の書き換えを生前に行った方が良いでしょう。
さて、次回は、相続放棄に関連して、「他の相続人による相続の承認又は放棄の期間の伸長申立」についてお話いたします。
それではまた!
未分割財産がある場合の遺留分の計算式
みなさんこんにちは!
名古屋もまだまだ寒い日が続いております。
風邪やコロナ、インフルエンザもまだまだ流行っておりますので、お体にはお気を付けください。
さて、本日は、前回に引き続き、遺留分に関して、「未分割財産がある場合の遺留分の計算式」についてお話していこうと思います。
まず、前回までの復習として、遺留分額の計算式としては、
遺留分=「遺留分を算定するための財産の価額(基礎財産額)」×「個別的遺留分割合」となります。
また、「基礎財産額」については、「被相続人が相続開始時において有した財産の価額」+「被相続人が贈与した財産の価額」-(相続債務の全額)となります。
具体的な遺留分侵害額については、
遺留分侵害額=「遺留分額-遺留分権利者が受けた贈与・遺贈・特別受益の額」-「遺産分割の対象財産がある場合において遺留分権利者の具体的相続分に相当する額」+「遺留分権利者が負担する債務(遺留分権利者承継債務)」となります。
この点、「遺産分割の対象財産がある場合において遺留分権利者の具体的相続分に相当する額」について、未分割財産があった場合の処理について、今回お話していきます。
さて、前置きが長くなってしまいましたが、「遺産分割の対象財産がある場合において遺留分権利者の具体的相続分に相当する額」について、たとえば、以下の事例で考えてみます。
被相続人(父)
相続人:長男、長女
遺言書の内容:長男に自宅土地建物を相続させる
遺産:自宅土地建物(時価7000万円)
預貯金1000万円
この場合、遺留分額としては、遺留分を算定するための財産の価額(基礎財産額)が合計の8000万円となり、長女の遺留分としては、その4分の1の2000万円となります。
ここで、遺言書の対象外となっている1000万円についてですが、そもそも、この1000万円をどう分けるのかについては、長男と長女との遺産分割の結果によります。
考え方の一つとして、長男は、遺言書によってすでに7000万円相当の自宅建物を相続しているため、残りの預貯金全てを長女が相続するということが考えられます。
他方、当該7000万円については、持ち戻し免除の意思表示がされているものとして、預貯金を500万円ずつで分けるという考え方もあります。
いずれの分け方にする方は、当事者間で話し合いがまとまらなければ、遺産分割審判で決着がつくことになります。
遺留分に関しては、仮に長女が1000万円を取得することになると、長女の遺留分の2000万円から1000万円を控除した1000万円が遺留分侵害額ということになります。
この場合、長女は、長男に対して、1000万円の遺留分侵害額請求を行うことになります。
さて、次回は、今回に引き続き遺留分に関して、よりマニアックな論点として、「未分割財産がある場合で、寄与分がある場合の遺留分の計算式」についてお話していこうと思います。
それではまた!
遺留分侵害額請求の計算式
みなさんこんにちは!
名古屋も時々、雪が降るなど、めっきり寒くなってきました。
インフルエンザやコロナ、風邪も流行っておりますので、みなさんもお体には十分にお気を付けください。
さて本日は、「遺留分侵害額請求の計算式」について、お話していこうと思います。
そもそも、遺留分とは、簡単にいうと相続人に認められた最低限度の権利のことをいいます。
また、遺留分の金額については、遺言書や生前贈与の内容、相続人の範囲、遺産の内容等で、大きく異なってきます。
以下では、簡単な事例を用いて、遺留分侵害額請求の計算式について、ご説明いたします。
【事案】
父が亡くなり、相続人は、長男と二男のみです。
父は、生前、長男家族と同居しており、長男家族が自身の介護をしてくれていたため、財産すべてを長男に相続させる旨の遺言書を残していました。
父は、令和7年2月1日に亡くなりました。
父の死後、長男は、父が残した遺言書どおりに遺産を分ける旨を二男に伝えたところ、二男は、長男に対して、遺留分侵害額請求をしました。
【父の遺産】
父の相続開始時(亡くなった時点)の遺産内容は、以下のとおりです。
自宅土地建物 時価3000万円(固定資産税評価額は2400万円)
預貯金 1100万円
父の医療費(死後に支払い) 10万円
父から長男からの生前贈与(令和5年1月1日) 1000万円
【遺留分額の計算式】
遺留分額=「遺留分を算定するための財産の価額(基礎財産額)」×「個別的遺留分割合」となります。
「基礎財産額」については、「被相続人が相続開始時において有した財産の価額」+「被相続人が贈与した財産の価額」-(相続債務の全額)となります。
1 基礎財産額について
自宅土地建物などの不動産の評価については、原則、時価を基準に評価します。
もっとも、遺留分請求者(二男)と遺留分を請求される人(長男)が合意をすれば、固定資産税評価額を基準にすることができます。
今回は、長男と二男との間で合意がまとまらなかったとして、時価を基準に評価します。
そのため、自宅土地建物の不動産価格は、3000万円となります。
よって、基礎財産額は、5090万円となります(遺産額に生前贈与を加え、債務を減額した額)。
2 個別的遺留分割合
二男の法定相続分は、2分の1であり、その半分の4分の1が個別的遺留分となります。
3 二男の遺留分請求額
よって、二男の遺留分額は、1272万5000円となります。
このように、遺留分の計算方法としては、それほど複雑ではありませんが、計算式を間違えてしまうと、遺留分額も変わってしまうため、注意が必要です。
さて、次回は、今回に引き続き、「未分割財産がある場合の遺留分の計算式」について、お話していこうと思います。
それではまた!
遺留分対策③~養子縁組の活用
みなさんこんにちは!
名古屋も含めて、緊急事態宣言が続くなか、みなさんはいかがお過ごしでしょうか。
私は、ジムでの筋トレができないため、自宅で筋トレを行っております。
少しでも早く、コロナが終息することを願うばかりです。
さて、本日は、前回に引き続きまして、遺留分対策に関するお話として、「遺留分対策③~養子縁組の活用」について、お話していこうと思います。
1 養子縁組を活用すれば遺留分額を減らすことが可能!
結論から申しますと、養子縁組を活用すれば、遺留分額を大幅に減らすことができます。
具体的には、相続財産の額にもよりますが、遺留分額を半分にすることも可能になります。
2 養子縁組を活用した場合の具体例
たとえば、父と長男と長女がいる家庭で、父が長男に全財産を渡すという遺言書を残したケースで考えてみます。
父の財産は、自宅の土地と建物(3000万)、預貯金(1000万)あります。
被相続人:父
相続人:長女、長男
父の財産:自宅の土地と建物(3000万)
預貯金(1000万)
この場合、父が亡くなった後、長女は長男に対して、遺留分侵害として、1000万円を請求することができます。
他方、長男に子が2人おり、父と長男の子(父から見て孫)が養子縁組をした場合、相続人は、長男、長女、孫2人の、合計4人となります。
そのため、遺留分額は、500万円となります。
このように、養子縁組をし、養子を増やすことによって、遺留分額を大きく下げることが可能になります。
3 養子縁組をする際の注意点
養子縁組をする場合、養子の数を多くしすぎた場合や純粋に遺留分対策の目的のためだけに養子縁組をする場合は、養子縁組が後々、無効になる可能性があります。
たとえば、亡くなる直前に5人と養子縁組をした場合などは、養子縁組が無効になる場合があります。
このように、養子縁組については、遺留分対策として、高い効果を発揮する反面、注意点も存在します。
そのため、遺留分対策で養子縁組を活用する場合は、一度、相続に詳しい専門家にご相談されることをおすすめします。
さて、次回は、問題になる遺言として、「財産の一部しか記載されていない遺言書」について、お話していこうと思います。
それではまた!
遺留分対策②~生前贈与の活用
みなさんこんにちは!
名古屋も含め、全国的にコロナウイルスの感染者が増加しており、まだまだ気が抜けない状況です。
一刻も早く、ワクチンが一人でも多くの方に行き渡ることを願うばかりです。
さて、今回は、前回と関連して、「遺留分対策②~生前贈与の活用」についてお話していこうと思います。
結論から言いますと、遺留分対策をする場合は、できるだけ早い段階から、相続人や他の親族に生前贈与をすることをおすすめします。
理由としては、なるべく早めに生前贈与をしておいた方が、遺留分請求額を大きく減らすことが可能になるためです。
そもそも、遺留分を計算するためには、亡くなった当時の遺産総額に、一定の生前贈与を加え、債務を控除して、遺留分の基礎となる財産額を計算します。
そのため、基本的に遺留分額を減らすためには、遺産総額を減らし、かつ、一定の生前贈与にも当たらないようにする必要があります。
ここで、前回は、保険を活用して、遺産総額を減らすことをご説明しました。
そこで、今回は、生前贈与を使って遺産総額を減らし、かつ、一定の生前贈与にも当たらない方法について、ご説明します。
1 生前贈与を全く使わなかった場合
まず、簡単な事例として、父と子供2人(息子と娘)、財産は、自宅が2000万、預貯金が2000万円という事例を使ってご説明します。
父の希望としては、娘にすべての財産を渡したく、遺留分対策もしたいとのことでした。
この場合、父が娘にすべての財産を渡す遺言書を書き、亡くなった場合、息子は娘に対して、遺留分として、1000万円を請求することができます。
計算式としては、遺産総額4000万円の4分の1が遺留分額となります。
【家族構成】
父、息子、娘
【相続財産】
自宅(2000万円)
預貯金(2000万円)
【遺留分額】
1000万円
2 生前贈与を活用した場合
この場合、生前贈与を活用することによって、遺留分額を大幅に減額できる可能性があります。
たとえば、父が娘に自宅を贈与し、その11年後に、父が亡くなったとします。
この場合、基本的に11年前の自宅の贈与は、遺留分の計算の対象外(「一定の生前贈与」には当たらない)となり、遺留分額は、500万円となります。
【家族構成】
父、息子、娘
【相続財産】
自宅(2000万円)
→11年前に娘に贈与
預貯金(2000万円)
【遺留分額】
500万円
3 遺留分の計算の対象外となる生前贈与とは
このように、生前贈与を活用することによって、遺留分額を大きく減らすことが可能です。
ここで、遺留分の計算の対象外(「一定の生前贈与」に当たらない)となる生前贈与について、ご説明します。
基本的に、相続人に対する10年以上前の贈与、相続人以外の者に対する1年以上前の贈与は、遺留分の計算の対象外となります。
そのため、先ほどの事例でいうと、たとえば、自宅を娘ではなく、娘の子供(孫)に贈与した場合、基本的に、その贈与が父の亡くなる1年以上前だと、遺留分の計算の対象外となります。
もっとも、注意点として、たとえば、父が亡くなる11年前に当時の全財産を贈与してしまった場合は、例外的に遺留分の計算の対象となる場合があります。
また、このことは、相続人以外への贈与についても同じです。
そのため、生前贈与に関しても、やりすぎてしまった場合は、遺留分対策として効果が生じない可能性がありますので、遺留分対策として、生前贈与を行う場合は、一度、専門家にご相談されることをおすすめします。
これまでのお話をまとめますと、基本的に、10年以上前の相続人への生前贈与と、1年以上前の相続人以外の人への生前贈与は、遺留分の計算の対象外となります。
もっとも、生前贈与の額によって、遺留分の計算の対象となる場合もあるため、注意が必要です。
そのため、遺留分対策として、生前贈与を活用される場合は、できるだけ早い段階から、相続人や相続人以外の人に生前贈与を行っておくことをおすすめします。
さて、次回は、今回と関連して、「遺留分対策③~養子縁組の活用」についてご説明していこうと思います。
それではまた!
遺留分対策①~保険の活用
みなさんこんにちは!
名古屋も含め、全国で緊急事態宣言が解除されましたが、まだまだ感染者は増加傾向にあるため、油断ができない状態です。
当法人では、引き続き、コロナ対策として、従業員のマスク着用の徹底、出勤時の検温チェック、定期的な空気の入れ替え等を行っております。
また、電話やメールでのご相談やビデオ通話でのご相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
さて、本日は、遺言書を作成するうえで、切っても切り離せない課題として、「遺留分対策①~保険の活用」と題して、お話していこうと思います。
そもそも遺留分とは、簡単に言うと、相続人に保証されている最低限度の相続の権利のことをいい、たとえ、遺言書で何も財産を渡さないと記載されていても、遺留分は認められます。
この遺留分は、しっかり対策をしておかないと、財産を渡された相続人にとって大変なことになるかもしれません。
なぜなら、遺留分はお金で支払わなければならず、お金が支払えない場合は、遺産を売るか、借金をしてでも払わなければならないためです。
例えば、父と長男、長女の家庭で、遺産について、預貯金500万円と自宅(父と長男家族が同居していた、価値は3500万)のみのケースで、父が長男に全財産を渡す遺言書を作成した場合について考えてみます。
家族構成 父 長男 長女
遺産 預貯金500万
自宅(3500万)
遺言書の内容 長男にすべてを相続させる
この場合、長女は、長男に対して、遺留分侵害として、遺産の4分の1に当たる1000万円を請求することができます。
長男としては、遺産の500万円だけでは、請求額に満たないため、長男の手持ちの財産から残り500万円を支出するか、自宅を売るなどしてでも、500万円を返さなければなりません。
こうなってしまうと、長男としては、遺言書で財産はもらったが、自宅を手放さなくてはならなくなるかもしれず、非常に困った事態になります。
そのため、遺言書を作成する場合は、遺留分も考慮して、ご生前中からしっかり、遺留分対策を行う必要があります。
さて、前置きが長くなりましたが、具体的な遺留分対策としては、まず、生命保険を活用することが考えられます。
具体的には、預貯金を生命保険に変え、生命保険の受取人を、遺産を受け取る相続人の一人にしておくことが考えられます。
生命保険は、原則、遺産の対象になりませんので、預貯金を生命保険に変えることで、遺留分の額を減らすことができます。
先ほどの家庭(父と長男、長女、遺産は預貯金500万円と自宅(3500万円)で、預貯金を生命保険に変えた場合について、検討します。
家族構成 父 長男 長女
遺産 預貯金500万
自宅(3500万)
遺言書の内容 長男にすべてを相続させる
遺産の総額は、3500万円となり、遺留分は、その4分の1の875万円となります。
このように、預貯金を保険に変えるだけで、遺留分の額を125万円減額することが可能です。
そのため、遺留分対策をする場合は、預貯金を生命保険に変えることが有効となります。
もっとも、ここで気を付けていただきたい点として、生命保険金の額が遺産に比して著しく多い場合は、例外的に生命保険金が遺留分の対象に含まれる場合があります。
たとえば、遺産が2000万円の家庭で、生命保険金が2000万円の場合、生命保険金も遺留分の対象になる可能性があります。
そのため、遺留分対策として保険を活用する場合は、一度、弁護士等の専門家にご相談することをおすすめします。
以上のように、遺留分対策として、生命保険の活用は非常に有用でありますが、使い方を間違えてしまうと、遺留分対策にならない場合もあるため、注意が必要です。
さて、来月のテーマは、遺留分対策のパート②として「遺留分対策②~生前贈与の活用」についてお話していこうと思います。
それではまた!
- 1