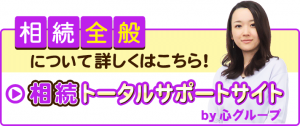他の相続人による相続の承認又は放棄の期間の伸長申立
みなさんこんにちは!
名古屋もだいぶ暖かくなり、もう夏かと思えるほどの気温の日も増えてきました。
みなさんも熱中症にはお気を付けください。
さて、本日は、「他の相続人による相続の承認又は放棄の期間の伸長申立」についてお話ししようと思います。
専門家でも知らない方がいますが、相続の承認又は放棄の期間の伸長申立(熟慮期間の延長の申立)については、相続の承認又は放棄を検討している相続人本人が行う必要はなく、他の相続人であっても、当該相続人のために、申立を行うことができます。
また、申立先の裁判所においても、あまりこの事実を知らない場合があり、書記官から「本当にできるのか」と質問されることもありますが、条文上、「利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所においてしんちょうすることができる。」と記載されており(民法915条1項)、利害関係人には、他の相続人も通常含まれるため、基本的に、相続の承認又は放棄の期間の伸長申立は可能です。
なお、私は、これまでも何件か、他の相続人による相続の承認又は放棄の期間の伸長申立を行いましたが、すべて認められています。
次に、実際に他の相続人による相続の承認又は放棄の期間の伸長申立を行う場合、だれの期間を伸長するのか、なぜ伸長するのかの理由と、申立を行う人本人の利害関係性について、申立書に記載する必要があります。
たとえば、伸長を行う本人が外国におり、すぐに相続放棄を行うのかどうかの判断がつかず、他の相続人が、当該外国にいる相続人の期間伸長の申立てを行う場合があります。
この場合、期間の伸長をする相続人本人が外国におり、自身で期間伸長の申立てを行うことが困難であること、他の相続人において、当該外国にいる相続人が放棄するのか、相続するのかは、一般に、自身の相続分も変化するため、利害関係を有することなどを申立書に記載します。
その後、必要書類(伸長をする相続人の戸籍謄本や申立人の戸籍謄本等)や印紙や郵券を添付し、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に、期間伸長の申立てを行います。
さて、次回は、遺言に関するお話として、「遺言における予備的条項の必要性」についてお話していこうと思います。
それではまた!